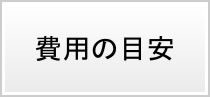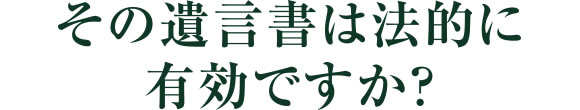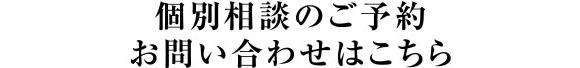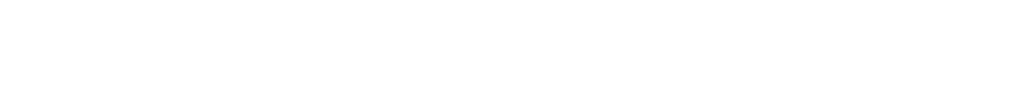
HOME > 必見! 遺言のススメ
今まで仲の良かった兄弟姉妹が、親の遺産を巡って骨肉の争いを繰り広げる。
これは決してテレビドラマの中だけの話ではありません。
この争いは遺産の額の多少に関わらず起こっています。
家庭裁判所の統計によると遺産分割調停に持ち込まれた案件の実に7割以上が5,000万円以下の遺産を巡る争いです。
遺産を巡る争いは親族に癒すことのない傷を負わせてしまいます。
ここに遺産の分配について明確に記した1通の遺言書があったらどうでしょう?
故人の遺志がここにあると判れば、相続人同士の争いの大部分が回避できるはずです。
内容に不満があったとしても「故人の遺志」と思えば納得せざるをえません。
不要なトラブルを避けることができるはずです。
これは決してテレビドラマの中だけの話ではありません。
この争いは遺産の額の多少に関わらず起こっています。
家庭裁判所の統計によると遺産分割調停に持ち込まれた案件の実に7割以上が5,000万円以下の遺産を巡る争いです。
遺産を巡る争いは親族に癒すことのない傷を負わせてしまいます。
ここに遺産の分配について明確に記した1通の遺言書があったらどうでしょう?
故人の遺志がここにあると判れば、相続人同士の争いの大部分が回避できるはずです。
内容に不満があったとしても「故人の遺志」と思えば納得せざるをえません。
不要なトラブルを避けることができるはずです。


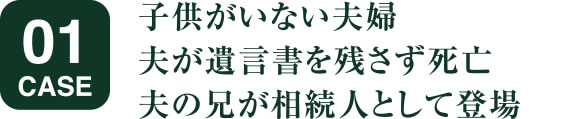
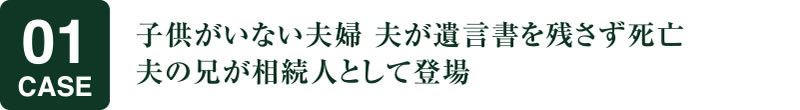

Aさんは結婚20年目で連れ添った夫をがんで亡くしました。
Aさんご夫婦には子供がいませんでした。
夫の両親は既に他界していました。
夫には疎遠になっている兄が一人いました。
Aさんご夫婦には夫名義の自宅マンションと定期預金が1,000万円ほどありました。
Aさんはもし万一夫が亡くなっても妻である自分一人が遺産を相続するものと信じ込んでいました。
夫の死後Aさんは銀行に行き、夫名義の預金を下ろそうとしましたが、窓口で告げられたのは、遺言書がなければ遺産分割協議書或いは当行の相続関係届書が必要です。
何れにしても義兄の署名、捺印(実印)、印鑑証明書が必要です。
ということだったのです。
Aさんは義兄に連絡を取ろうとしましたが、なかなか繋がりません。
結局手紙を書いて連絡を待ちました。
2週間後ようやく義兄から連絡がありました。
その後色々ありましたが結局判代として100万円を渡すことで決着しました。
その間のAさんのストレスは大変なものでした。
夫が「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成しておきさえすれば残された妻は苦労せずに済んだという話です。
Aさんご夫婦には子供がいませんでした。
夫の両親は既に他界していました。
夫には疎遠になっている兄が一人いました。
Aさんご夫婦には夫名義の自宅マンションと定期預金が1,000万円ほどありました。
Aさんはもし万一夫が亡くなっても妻である自分一人が遺産を相続するものと信じ込んでいました。
夫の死後Aさんは銀行に行き、夫名義の預金を下ろそうとしましたが、窓口で告げられたのは、遺言書がなければ遺産分割協議書或いは当行の相続関係届書が必要です。
何れにしても義兄の署名、捺印(実印)、印鑑証明書が必要です。
ということだったのです。
Aさんは義兄に連絡を取ろうとしましたが、なかなか繋がりません。
結局手紙を書いて連絡を待ちました。
2週間後ようやく義兄から連絡がありました。
その後色々ありましたが結局判代として100万円を渡すことで決着しました。
その間のAさんのストレスは大変なものでした。
夫が「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成しておきさえすれば残された妻は苦労せずに済んだという話です。
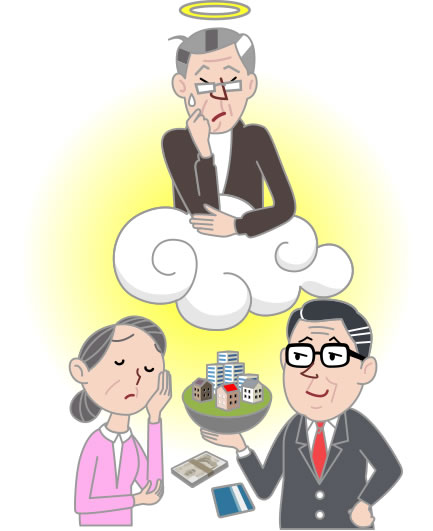
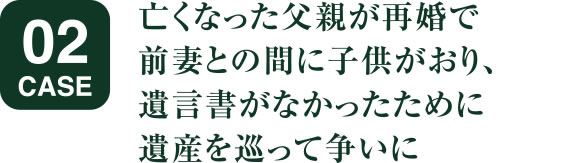
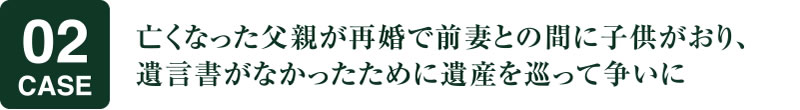

Bさんは一人っ子で、父親の相続人は母親と自分だけだと思っていまいした。
父親亡きあとは、父の残した実家で母親と同居し面倒をみるつもりでいました。
ところが、家の名義変更を進めていく中で、亡くなった父親は再婚で、別れた先妻との間に子供がいることが分かったのです。
Bさんはこの事実を知りませんでした。
母親は以前父親から再婚したこと、子供がいることを聞いていたらしいのですが、父親からもう縁を切った、赤の他人だと言われたたため安心していたとのことです。
父親も母親も赤の他人だと言い切った先妻の子供(Hさん)ですが、Bさんから見れば異母兄弟にあたり、法律上はBさんと同格の立派な相続人です。
Bさんは相続登記を依頼した司法書士(私)を通じてHさんの住所を知りました、そして手紙を書き連絡を待ちました。
数日後Hさんの代理人と称する弁護士から内容証明郵便が届きました。
遺産の開示を求めたうえで法定相続分を請求する。
1週間以内に返答がない場合には遺産分割調停を申し立てるという内容でした。
結局本件は調停に付され、2年近くの時を経たのち双方の合意で決着しました。
遺産の評価に争いがあったため鑑定を入れたり、財産目録の調製にも時間と労力を費やしました。
結局実家を守ることができたので、その点は良かったのですが、Bさんは大変な思いをしました。
父親が遺言を書いていてくれさえすればBさんの苦労はなかったはずです。
父親亡きあとは、父の残した実家で母親と同居し面倒をみるつもりでいました。
ところが、家の名義変更を進めていく中で、亡くなった父親は再婚で、別れた先妻との間に子供がいることが分かったのです。
Bさんはこの事実を知りませんでした。
母親は以前父親から再婚したこと、子供がいることを聞いていたらしいのですが、父親からもう縁を切った、赤の他人だと言われたたため安心していたとのことです。
父親も母親も赤の他人だと言い切った先妻の子供(Hさん)ですが、Bさんから見れば異母兄弟にあたり、法律上はBさんと同格の立派な相続人です。
Bさんは相続登記を依頼した司法書士(私)を通じてHさんの住所を知りました、そして手紙を書き連絡を待ちました。
数日後Hさんの代理人と称する弁護士から内容証明郵便が届きました。
遺産の開示を求めたうえで法定相続分を請求する。
1週間以内に返答がない場合には遺産分割調停を申し立てるという内容でした。
結局本件は調停に付され、2年近くの時を経たのち双方の合意で決着しました。
遺産の評価に争いがあったため鑑定を入れたり、財産目録の調製にも時間と労力を費やしました。
結局実家を守ることができたので、その点は良かったのですが、Bさんは大変な思いをしました。
父親が遺言を書いていてくれさえすればBさんの苦労はなかったはずです。
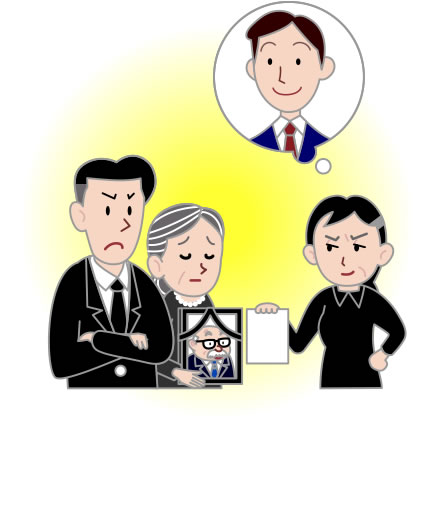
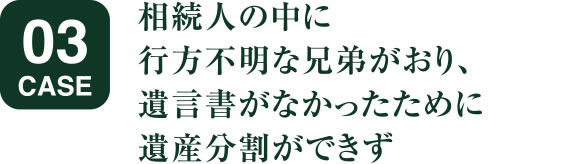
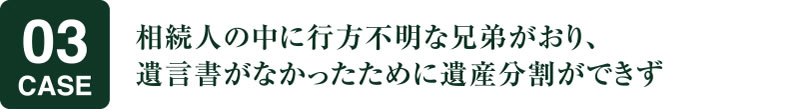
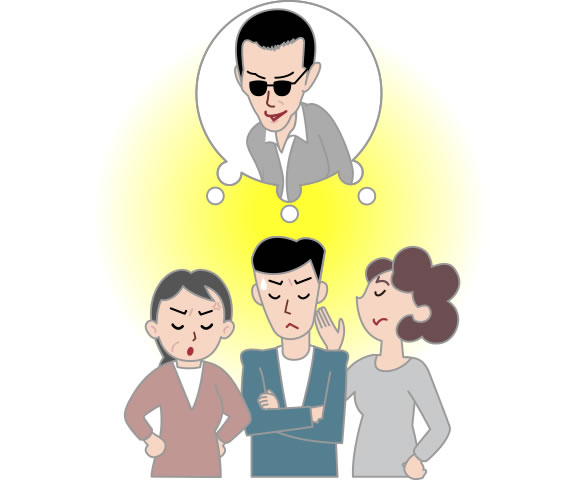
Cさんは3人兄弟の長男で、2歳下の妹と5歳下の弟がいます。
弟は素行が悪く親子喧嘩が絶えず、とうとう家を出て行ったきり音信不通になってしまいました。
晩年と父親は弟のことを気にかけて何とか行方を探そうとしましたが、結局行方不明のまま亡くなってしまいました。
葬式の前思い切って新聞広告を出しましたが、弟から連絡はありませんでした。
父親が亡くなって四十九日が過ぎたのを機会に母とCさん、妹の間で遺産相続の話になりました。
父の遺産は自宅と定期預金が2,000万円程ありました。
自宅は母親がそのまま住むことになるので母親名義に、預貯金は均等に分けようと決まりました。
ところが問題となったのは弟の存在です。
弟にも相続権があるため、弟の同意なしには自宅の名義変更も預金の払い戻しもできません。
遺産は凍結状態になってしまったCさんは、現在も興信所を使って身元捜しをするか家庭裁判所に不在者の財産管理人の申し立てを行うか迷っています。
父親が遺言書を書いておいてくれさえすればこのような事態にならなかったのにと悔しい毎日を過ごしています。
弟は素行が悪く親子喧嘩が絶えず、とうとう家を出て行ったきり音信不通になってしまいました。
晩年と父親は弟のことを気にかけて何とか行方を探そうとしましたが、結局行方不明のまま亡くなってしまいました。
葬式の前思い切って新聞広告を出しましたが、弟から連絡はありませんでした。
父親が亡くなって四十九日が過ぎたのを機会に母とCさん、妹の間で遺産相続の話になりました。
父の遺産は自宅と定期預金が2,000万円程ありました。
自宅は母親がそのまま住むことになるので母親名義に、預貯金は均等に分けようと決まりました。
ところが問題となったのは弟の存在です。
弟にも相続権があるため、弟の同意なしには自宅の名義変更も預金の払い戻しもできません。
遺産は凍結状態になってしまったCさんは、現在も興信所を使って身元捜しをするか家庭裁判所に不在者の財産管理人の申し立てを行うか迷っています。
父親が遺言書を書いておいてくれさえすればこのような事態にならなかったのにと悔しい毎日を過ごしています。
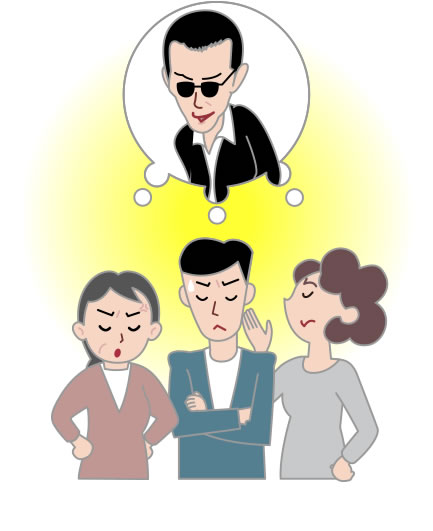
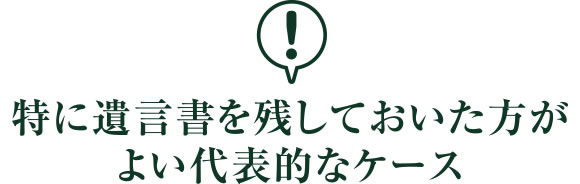


①
夫婦の間に子供がいない場合
このケースの相続人は、①配偶者と亡くなった夫(妻)の両親、②両親が亡くなっている場合は配偶者と亡くなった夫(妻)のご兄弟です。
特に②の場合が問題になります。
兄弟だけならまだしもその配偶者が口を挟んでくると話はややこしくなります。
さらに、もし兄弟が先に亡くなっていたら甥っ子、姪っ子が相続人に繰り上がってきます。
「財産を全て妻に相続させる」と言う遺言があれば安心です。
特に②の場合が問題になります。
兄弟だけならまだしもその配偶者が口を挟んでくると話はややこしくなります。
さらに、もし兄弟が先に亡くなっていたら甥っ子、姪っ子が相続人に繰り上がってきます。
「財産を全て妻に相続させる」と言う遺言があれば安心です。
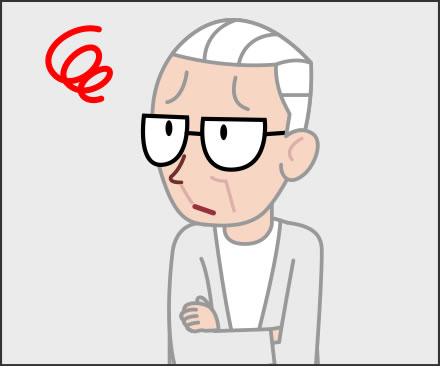
②
独り暮らしの方・身寄りのない(相続人がいない)方の場合
法律上相続人がいても交流のない場合も同様です。
生前世話になった方に財産をあげたい場合や福祉目的に遺産を役立ててほしい場合には、相手先をきちんと指定した遺言書を遺しておく必要があります。
生前世話になった方に財産をあげたい場合や福祉目的に遺産を役立ててほしい場合には、相手先をきちんと指定した遺言書を遺しておく必要があります。
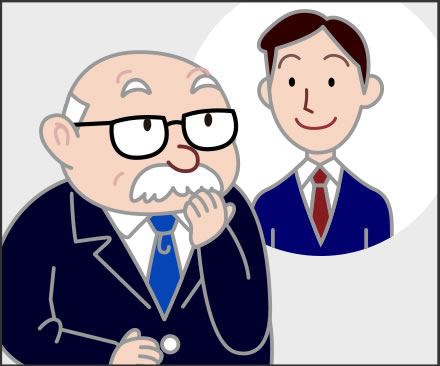
③
先妻との間に子供がいる場合
先妻との間の子供とは、つきあいが無いのが普通です。
むしろ他人以上に悪感情を持たれている場合が多いです。
この先妻の子供も相続人になるため、遺言が無ければ、遺産分割協議書に実印を押してもらわなければ不動産も預貯金も思うように相続することができません。
むしろ他人以上に悪感情を持たれている場合が多いです。
この先妻の子供も相続人になるため、遺言が無ければ、遺産分割協議書に実印を押してもらわなければ不動産も預貯金も思うように相続することができません。

④
息子の嫁に財産を譲りたい場合
生前一番世話になったのは長男の嫁であったとしても、嫁は相続人ではないため、遺言がなければ財産を譲ることはできません。感謝の気持ちを遺言書という形で残しておきましょう。
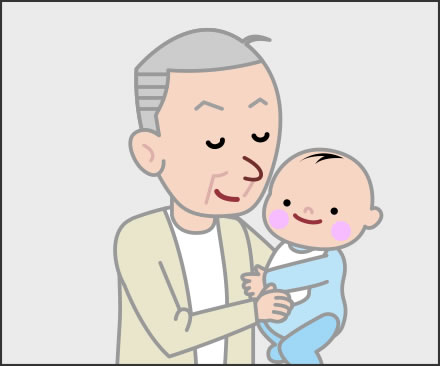
⑤
孫に財産を譲りたい場合
いくら孫がかわいいと言っても子供が生存している場合には、孫には相続権はありません。
遺言を残しておかなければ孫に財産を譲ることはできません。
遺言を残しておかなければ孫に財産を譲ることはできません。

⑥
内縁の妻(夫)に財産を譲りたい場合
内縁の妻(夫)には相続権はありません。
亡くなった場合は、遺産は全て親、兄弟のもとに行ってしまいます。
夫婦同然に暮らしていても事情があって入籍できないカップルもあります。
遺言書を書いておかなければ相手方に財産を遺すことはできません。
亡くなった場合は、遺産は全て親、兄弟のもとに行ってしまいます。
夫婦同然に暮らしていても事情があって入籍できないカップルもあります。
遺言書を書いておかなければ相手方に財産を遺すことはできません。

⑦
相続人の中に財産を譲りたくない者がいる場合
親子の縁を切ったと当事者や周りの者も認識しておいても、法律上は立派な相続人です。
従って相続人の中から廃除するためにはも遺言書を書いておかなければ効力がありません。
従って相続人の中から廃除するためにはも遺言書を書いておかなければ効力がありません。
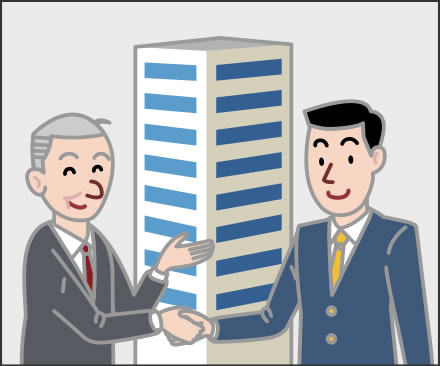
⑧
事業を継ぐ者に会社の株式や事業用財産を引き継ぎたい場合
経営者の相続の場合には、事業承継の視点も必要です。
事業が円滑に承継されるためには、経営権と事業用資産を後継者に引き継がなければなりません。
遺産分割でもめたりしてこれらが分散してしまわないようにしっかり遺言を残しておくことが経営者の責務です。
事業が円滑に承継されるためには、経営権と事業用資産を後継者に引き継がなければなりません。
遺産分割でもめたりしてこれらが分散してしまわないようにしっかり遺言を残しておくことが経営者の責務です。
公正証書遺言の場合には公証人が作成しますので、まず無効になる心配はありません。
気をつけたいのは自筆証書遺言の場合です。
せっかく書いた遺言書も法律上の要件を欠く場合には無効になってしまいます。
そうならない為に下記の遺言書チェックリストでご確認ください。
気をつけたいのは自筆証書遺言の場合です。
せっかく書いた遺言書も法律上の要件を欠く場合には無効になってしまいます。
そうならない為に下記の遺言書チェックリストでご確認ください。



表題は「遺言書」になっていますか?
遺言書の表題は無くても無効にはなりませんが、これが遺言であるということをはっきりさせる為にも表題は「遺言書」と書きます。
因みに遺言書を書く用紙は何でもOKです。
因みに遺言書を書く用紙は何でもOKです。

全文、日付、名前を自筆で書いていますか?
ワープロ、パソコン、ゴム印を使用してはだめです。

作成日付は明確ですか?
作成日付が不明な遺言は無効です。
例えば〇年〇月吉日などは無効です。
はっきりと〇年〇月〇日と記載しましょう。
例えば〇年〇月吉日などは無効です。
はっきりと〇年〇月〇日と記載しましょう。

遺言者の署名、押印がありますか?
遺言者本人の自筆署名と押印が必要です。
代筆やゴム印は無効です。
押印はできれば実印を用いましょう。
代筆やゴム印は無効です。
押印はできれば実印を用いましょう。

遺言内容を加筆、削除、訂正する場合は
民法所定の要件を満たしていますか?
民法所定の要件を満たしていますか?
遺言には厳格な訂正のルールが定められており、これを欠く場合は遺言全体が無効になってしまいます。
思い切って一から書き直す方がよい場合もあります。
思い切って一から書き直す方がよい場合もあります。

遺言書が複数枚にわたる場合、契印を押していますか?
法律上の規定はありませんが、遺言の同一性や欠落がないことを確認するためにも、署名欄と同じ印鑑で契印しておきましょう。

遺言者はお一人ですか?
夫と妻がお互いの為に遺言を書く場合であっても同じ書面に書いてはだめです。必ず別々の文書で作成してください。

財産を特定できる記載内容になっていますか?
例えば、不動産の場合は登記簿謄本どおり(自宅ではだめ)、預貯金は、金融機関、支店名、口座番号を特定する。

相続人を特定していますか?
単に長男、次男と書くのではではなく、遺言者との続柄、氏名(生年月日)を書いてください。

遺言書を書き終えたら、封筒に入れ
押印しましたか?
押印しましたか?
書き終えた遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印する事をおすすめします。
ここで押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。
ここで押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。

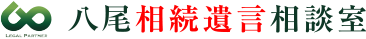
運営:司法書士法人リーガルパートナー
代表:司法書士 加藤俊夫
代表:司法書士 加藤俊夫
本店八尾オフィス 大阪府八尾市山本町北3-3-6 TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558
大阪梅田オフィス 大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース19階 TEL:06-7668-8542
大阪梅田オフィス 大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース19階 TEL:06-7668-8542
本店八尾オフィス
大阪府八尾市山本町北3-3-6
TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558
大阪梅田オフィス
大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース19階
TEL:06-7668-8542
大阪府八尾市山本町北3-3-6
TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558
大阪梅田オフィス
大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース19階
TEL:06-7668-8542
Copyright© 八尾相続遺言相談室 all rights reserved.